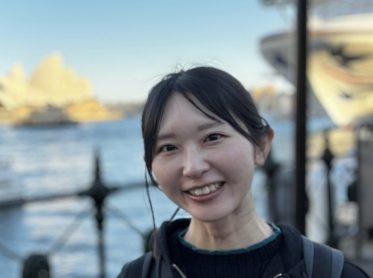
第107回TQE 特許明細書・化学(英文和訳)
永峯さん
1.自己紹介をお願いします
第107回TQE「特許明細書(化学)」英文和訳に合格しました、永峯と申します。法学部を卒業後、金融機関に就職し、出産を機にフリーランスになりました。現在は、株式会社サン・フレア様で特許校正者としてお仕事をさせて頂いています。
2.受検した言語の学習歴を教えてください
中学校から大学まで英語は一貫して好きな科目でした。就職活動前に英語を「話せる」ようになろうと半年間の英国留学へ。流暢にとまではいきませんが、旅行には困らない程度に底上げができたと思います。何より、語学学校で知り合った国際色豊かな学生たちから多くの刺激を受けました。帰国後に彼らと変わらずコミュニケーションを図るためには英語力の維持が肝心です。社会人になってからも英語を頻繁に使用する職場に身をおき、定期的にTOEICや英検を受けるなどして学びを絶やさないよう心がけていました。
3.翻訳の学習歴を教えてください
フリーランスになってすぐ、初級講座「はじめての翻訳技法」を受講しました。もう8年も前のことになります。その後、特許校正者としてお仕事をさせて頂くようになってから、初級講座「はじめての特許翻訳」を通じて特許分野の翻訳に関する特徴を学びました。また近年は翻訳支援ツールについても知識を深めておく必要性を強く感じるようになり、特別講座「Trados 2021」も受講しました。その他、特許翻訳に関する雑誌や書籍も複数購入して手元においておき、疑問が生じるたびに参照するようにしています。
4.何がきっかけで翻訳者を目指そうと思いましたか
前職での業務の一部に、英文レポートを抄訳して同僚に共有するという作業がありました。この作業がとても面白く、またストレスを感じることも無く取り組めていたため、いずれは翻訳関連の仕事に転職したいと思うようになりました。
5.TQEを受検したきっかけは何ですか
翻訳に関する情報収集をしていた折に、実力を客観的に評価して頂ける機会としてTQEを知りました。設けられた期間内に調査をして、翻訳文を作成する形式は実務に似ており、語学力だけでなく翻訳者にとって必要な調査能力とスピード感も訓練できると感じました。翻訳のスキルを伸ばすことは間違いなく校正の仕事にもプラスの影響があると思い、挑戦してみることにしました。
6.TQE合格のために苦労した点、悩んだ点はどういったことでしょうか
合格のためには、致命的な誤訳を避けることが大切だと思います。私の場合、修飾関係のミスが多発しており、それが致命的な誤訳と解釈されかねないと講評にてコメントを頂いていました。化学の知識不足や、発明への理解が浅いために、訳文作成時には修飾関係の誤りに気が付けなかったのです。特に、欠落している化学の知識をいかにして吸収していくかは長く悩みました。また、限られた試験期間内に発明を正しく理解するための調査方法や作業のスピード感も手探りでした。不合格の結果を連続で受け取ると、自分は翻訳に向いていないのではないかという感覚に陥ることもあり、モチベーションを保つのが難しい時期もありました。
7.苦労した点、悩んだ点はどのように解決されましたか
「また不合格かも」という不安はいったん置いておき、「合格は今回じゃなくても良いから自分なりに筋の通った翻訳をしよう」と気持ちをいれかえると、落ち着いて原文に向き合えるようになりました。ネックだった化学の知識に関しては、高校化学の教科書を購入し、目を通してみました。通読を終えたころには不思議と化学という教科がとても魅力的なものに思え、次第に苦手意識が薄れていきました。また、発明への理解を深めるため、訳文作成時間の大半を調査にあてました。先に仮訳し、疑問点を中心に調査を行うとその後の見直しも集中して進められたので、自分にはこの作業方法が合っていたのだと思います。
8.合格した分野を受検するために参考にした書籍等はありますか
まずは高校化学の教科書(『化学基礎』『化学』(啓林館))です。それから、特許制度と特許分野で翻訳の対象となる文書の種類を知るのに雑誌『特許翻訳完全ガイドブック』(イカロス出版)が役立ちました。発明の理解を深めるためには、「Google Patents」で関連発明の明細書を参照したり、発明が属する技術分野で業界をリードしている企業のウェブサイトで情報を収集したりしました。
9.翻訳者としてのこれからの計画を教えてください
お仕事を頂けたら真摯な取り組みを心がけ、回数を重ねていくうちに自分に合った翻訳のペースを掴んでいけたらと思っています。自身の力量を考えるとまだまだ先の話にはなりそうですが、同分野の和文英訳にも対応できる翻訳者になれたら嬉しいです。
10.TQE合格を目指す方々にメッセージをお願いします
合格までの道のりを振り返ってみると、過去に頂いた講評の分析がとても重要だったことに気が付きました。【個別事項】の記載内容は、現時点でのウィークポイントであり、伸びしろでもあります。それを克服する方法をさがし、粛々と実践してみると、大きな成長が待っているように思います。また、TQEではわずかな減点が合否を分けます。提出前にあらためて原文と訳文の突合を行うだけでも、訳抜け、訳ゆれ、変換ミスなどのスタイルに関連する減点を防げるので、「よし、訳文ができた」と思ってからさらに一回追加で最後の見直しを試みることは非常に有効だと思います。
